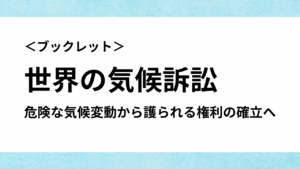ICJ、気候変動で歴史的判断 国の「法的責任」を明示 ―気候正義の新時代に向けて―
2025年7月25日
特定非営利活動法人 気候ネットワーク
代表 浅岡 美恵
2025年7月23日(オランダ時間)、オランダ・ハーグにおかれた国際司法裁判所(ICJ)は、気候変動に関する国の義務についての勧告的意見を発表した。これは2023年3月に国連総会から要請を受けていたものである。
勧告的意見では、「『可能な限り高い野心』という基準は、各国の裁量に委ねられているわけではなく、各国は 1.5°C の目標達成に最大限の努力を払わなければならない」ことや、「私的行為者の活動を規制する国家の義務が含まれ、気候変動に悪影響を与える排出を行う民間企業を規制しなかった場合、各国は責任を問われる可能性」について言及されており、世界第5位の排出国である日本や大規模排出事業者の責任にも向けられたものであり、今後の日本の気候エネルギー政策転換の必要性を裏付ける重要な判断が下されたと言える。
ICJが「健康な環境への権利」を拘束力ある国際法規範と認め 、将来世代への配慮義務を明確にしたことは、政府の気候変動対策の不十分さを問う上で極めて重要な論拠となる。日本の司法においても、この権威ある国際的な判断が反映されることが求められる。
今回の勧告は、気候危機の最前線に立つバヌアツや太平洋の若者たちが、勇気をもって声をあげ、世界を動かした成果である。気候変動の影響に苦しむすべての人々、企業の無責任な化石燃料ビジネスの被害を受けるすべての地域社会、未来に希望をつなげようとする若者たちを後押しするもので、法を気候正義の側に引き寄せるものだ。
勧告的意見に至る経緯
危険な気候変動への対処には国際的な協力が欠かせない。気候災害が頻発、甚大化するなか、国連では、気候変動枠組み条約の下での国際交渉によって国際合意を積み上げ、世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑える努力が続けられてきた。しかし未だ、各国の削減目標はその経路から大きく乖離し、2024年には世界の平均気温が単年で1.5℃を超え、日本でも気候災害がさらに激化するなど、気候危機は深刻化している。
こうした状況を受け、国際社会では気候変動と人権の関連性を重視し、国や民間企業の気候変動対策を法的義務として捉える動きが広がっている。国連人権理事会で2021年10月8日に、43票の賛成で、安全、清潔、健康的かつ持続可能な環境に対する権利を、諸人権の享受にとっての重要な人権として認識するとの決議が採択された。国連子どもの権利委員会は、2023年8月28日、深刻化する気候危機を受けて、環境と子どもの権利に関し、子どもの権利条約に基づく締約国の義務についての包括的な解釈を示した「一般的意見26」(2023年)を公表するなど、国連としての動きも重ねられてきた。さらに以下に紹介する通り、近時、国際司法機関において勧告的意見が出されてきた。
欧州人権裁判所決定 2024.4.9
欧州人権条約第8条の個人生活及び家庭生活の権利には、気候変動が生命、健康、福祉及び生活の質に及ぼす深刻な悪影響から国家当局による効果的な保護を受ける権利が含まれていると認定し、国の排出削減義務を明示し、NGOの申立権を認め、スイス国の2030年削減目標を不十分とした。
国際海洋法裁判所勧告的意見 2024.5.21
・人為的GHGの排出は海洋汚染に該当
・国連海洋法条約(UNCLOS)第194条第1項に基づき、締約国は、人為的な温室効果ガス排出による海洋汚染を防止し、削減し、及び規制するために必要なすべての措置(相当の注意:当該排出による海洋環境への深刻かつ不可逆的な損害のリスクが高く、厳格な義務と、これに関連して政策の調和を図るよう努める)に対して特定の義務を負う。
米州人権裁判所勧告的意見 2025.7.3
米州人権裁判所は2017年に、健全な環境への権利は人権であるとしていたが、2025年7月の気候緊急事態における国家の人権義務に関する勧告的意見ではさらに踏み込み、以下を指摘した。
・健全な環境への権利には安定した気候への権利が含まれ、地球温暖化が1.5℃を超えると複数の人権の享受が脅かされる
・各国は米州人権条約及びサンサルバドル議定書に基づき、気候変動による人権への影響を防止、緩和、救済する義務を負う
・気候科学と整合した効果的な緩和・適応措置を講じ、民間主体を規制し、特に衡平性と共通だが差異ある責任の原則に基づき他国と協力しなければならない
・情報へのアクセス、市民参加、司法へのアクセスを含む手続上の保障の必要性を強調し、先住民族、アフリカ系コミュニティ、子ども、環境保護活動家、そして将来世代に対する特別な保護の重要性
国連総会から国際司法裁判所に勧告的意見を要請
2023年3月、100カ国以上の共同提案により、国連総会は国際司法裁判所に勧告的意見の発出を求める決議を採択した。この決議は、南太平洋の若者たちをはじめとする国際的な若者の運動(World’s Youth for Climate Justice)が、2021年から粘り強く各国に働きかけてきた成果である。(A/RES/77/276)。
国際司法裁判所へ提出された質問は、以下のような内容であった。
● 国家及び現在及び将来の世代のために、人為的な温室効果ガス(GHG)排出から気候システムや環境を確実に保護するための国家の義務は何か
● これらの義務の下で、その作為および不作為によって、気候システムおよび環境に重大な損害を与えた場合、以下との関係における帰結とは何か
a) 気候変動の悪影響により、地理的状況や開発レベルのために、被害や影響を受ける、あるいは特に脆弱な状況に置かれている国々、特に小島嶼開発途上国(SIDS)
b) 気候変動の悪影響を受ける現在および将来世代の人々と個人
今回の国際司法裁判所の勧告的意見は、これらの国際機関の意見を取り入れつつ、気候危機を回避する文脈で、国、さらに企業の責任とその法的責任の内容とその不履行における帰結について整理したものである。異なる意見を述べる国もあるなか、全会一致での判断であり、法的責任の根拠に慣習法やデューデリジェンスを重視した、気候変動と人類の危機に対するすべての国、そしてその管理下にある企業についての法的責任の新たな時代を開くものとなるであろう。
多くの相互に関連する論点があり、内容も多岐にわたるが、日本の気候変動政策との関係で注目すべき点を以下に指摘する。
勧告的意見の注目点
- 関連する準拠法は、気候変動条約、京都議定書、パリ協定のみとする一部の国の主張を退け、人権法、海洋法、国際環境法、その他の環境条約も気候変動義務を規律すると確認した。
- 1.5℃目標はパリ協定の下での科学的根拠に基づく締約国が合意した気温目標であり、締約国のNDCの内容は、過去の温室効果ガスの累積排出量、締約国の発展のレベル、国情に照らし、気候目標の達成に十分貢献できるものでなければならない。
- 各国のNDCの目的達成の義務は実質的なものであり、この義務の遵守は、民間主体によって行われる活動を含め、入手可能な最善の科学、リスク、能力などを考慮し、厳格なデューデリジェンスを通じて、気候システムへの重大な被害を防止しなければならない。
- 「可能な限り高い野心」という基準は、各国の裁量に委ねられているわけではなく、各国は 1.5°C の目標達成に最大限の努力を払わなければならない。
- 気候変動の文脈で国家に求められるデューデリジェンスは、適切な規制と措置、共通だが差異ある責任とそれぞれの責任能力の原則、起こりうる危害の可能性と深刻さに関する科学的情報に基づく。
- 国際慣習法による国の越境的環境被害防止義務は、環境に対する重大な危害が、他の国家や民間行為者による累積的影響による気候システムの保護にも適用される。
- 国家間の協力は、条約及び国際慣習法に基づく義務であり、気候変動に関する有意義な国際的努力の基盤そのものである。
- 気候変動の悪影響は、生命、健康への権利、食糧、水、居住へのアクセスを含む適切な生活水準を確保する権利、プライバシー、家族、家庭への権利、女性、子ども、先住民族の権利の共有を著しく損なう可能性がある。気候変動が人権の共有に及ぼす影響から、気候システム及びその他の環境の保護なしに、人権の完全な享受を確保することはできない。人権義務を履行する際に、条約及び国際慣習法に基づく義務を考慮しなければならない。
- 各国は、条約上及び慣習法上、気候システムに対する重大な危害を防止する義務があり、これらの義務は、開発状況や過去の排出量に関係なく、気候変動条約の締約国ではない国も含め、すべての国に適用される。
- 気候系を含む環境への重大な危害を防止する第一義的義務の履行において、デューデリジェンスを行わない国は国際的な不法行為を犯すことになる。ここに、私的行為者の活動を規制する国家の義務が含まれ、気候変動に悪影響を与える排出を行う民間企業を規制しなかった場合、各国は責任を問われる可能性がある。
- 国家は、気候変動条約、その他の関連する環境条約および慣習法に基づく義務を実施する際には、国際人権法に基づく義務を考慮しなければならないと強調した。
- 気候変動による損害は複数の国家および主体からの累積的な排出によって引き起こされるが、各国家は依然としてその貢献度に応じて個別に責任を問われる可能性がある。歴史的排出量と現在の排出量の両方を考慮することで、世界全体の排出量に対する各国の総貢献度を決定することは科学的に可能である。
- 気候変動の文脈において、裁判所は、被害を受けた各国は、国際的に不法な行為を行い、気候システムに悪影響をもたらした各国に対して、個別に責任を主張することができると考える。
- 損害の因果関係はこのような責任を決定するための要件ではなく、賠償を決定するうえでの法的概念である。不法行為と損害との間に十分に直接的かつ確実な因果関係の存在が求められるが、気候変動という現象に関して生じる課題に、十分に柔軟であり、因果関係の特定が不可能であることを意味するものではない。
- 気候変動緩和義務はあらゆる人に対する普遍的な国際法上の義務(erga omnes)であり。その義務違反に対する責任は、いかなる国も行使できる。
- 国際慣習法上、不法行為を行った国家は、その不法行為が継続中であり、かつ違反した義務が有効である場合、その行為を中止する義務を負う。
気候関連の不法行為に責任を負う国家は、完全な賠償(賠償、補償、またはその組み合わせ)を提供することが求められる可能性がある。
国際司法裁判所による今回の勧告的意見は、各国および企業に対する気候変動における法的責任の内容とその履行の必要性を明示したものであり、気候危機時代における国際法の新たな基準を提示する歴史的な判断といえる。とりわけ、バヌアツなど小島嶼国などの甚大な被害に曝されている国や地域の人々の正義を実現していくために、新天地を開く可能性がある。
日本で若者たちが電力事業者10社に対し、1.5℃目標に整合する排出削減を求めて提起した若者気候訴訟にも、今回の国際司法裁判所の示したパリ協定やグラスゴー気候合意と国際慣習法や人権法を包摂した国や民間企業の責任やデューデリジェンスの実質的実施を求める意見は大きな力となるだろう。
参考
ICJプレスリリース:The Court gives its Advisory Opinion and responds to the questions posed by the General Assembly
和訳はこちら:
【プレスリリース】国際司法裁判所「気候変動に関する国家の義務についての勧告的意見」暫定和訳の公開について(2025年8月20日) | 気候ネットワーク
お問い合わせ
本プレスリリースについてのお問い合わせは以下よりお願いいたします。
特定非営利活動法人 気候ネットワーク
(京都事務所)〒604-8124 京都市中京区帯屋町574番地高倉ビル305号(→アクセス)
(東京事務所)〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目12番2号藤森ビル6B(→アクセス)
075-254-1011 075-254-1012 (ともに京都事務所) https://kikonet.org