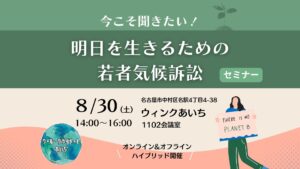2025年7月23日
特定非営利活動法人 気候ネットワーク
代表 浅岡 美恵
気候ネットワークは、資源エネルギー庁が実施している次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 制度検討作業部会 第二十二次中間とりまとめ (案)(長期脱炭素電源オークションについて)に対する意見募集に対して以下の意見を提出しました。
意見内容
1.総論(長期脱炭素電源オークションの枠組について)
長期脱炭素電源オークションは、2050年までのカーボンニュートラル達成を見据えて、化石燃料からの脱却と再エネシフトに向けた動きを加速するしくみであるべきだ。しかし、現行のオークションは、既存石炭火力やLNG火力を維持する改修やLNG火力の新規建設を促し、、原子力発電の安全対策に投資することで既設原発を維持し、時間もコストもかかる原発の新増設を促すもので、再エネシフトを促進することなく(太陽光・風力などの落札はこれまでゼロ)抜本的な見直しが必要である。しかも、今回の第三回オークションの見直しは、こうした誤った構造に拍車をかけるもので、非常に問題が多い。この取りまとめ案に反対する。
2.対象について(P7~)
①CCS付火力の20%回収設備の対象化は既存の石炭火力の延命策なので反対
第3回入札での対象に既設火力をCCS付火力に改修することを対象にする案が提示された。しかもCO2回収率はわずか20%以上と非常に低く、これを対象とするのは反対である。
IPCC第6次報告書では「対策のとられた石炭火力」とは、「90%以上CO2を回収できる設備」としている。それにもかかわらず本取りまとめでは「技術的には100%に近いCO2回収率を実現することは可能だが、 既設火力を改修して CCS化する場合は、敷地条件により CCS化に必要な設備(CO2 の分離回収設備や蒸気供給用のボイラー等)の設置に制約が生じる場合があること等を踏まえれば、100%のCO2 回収率を求めることは適切ではない」とし、一方で「あまりに低いCO2 回収率を許容するのは、脱炭素化を促進する制度として望ましくない」としながら、アンモニア混焼20%と同程度という無意味な理由を持ち出し、対策がとられたとは言えないような、あまりに低いCO2回収率での改修を推進しようとしている。これは、アンモニア混焼同様、既存石炭火力の延命措置にほかならず、CO2の排出固定化につながるため、「脱炭素電源」などと言えない。
さらに、「対象kWから生じるCO2 発生量のうち、年間で7割以上は実際にCO2を貯蔵まで行うことを求め、これを下回る場合は容量確保契約金額について1・2割の減額を行うペナルティを設定した」と、貯蔵量が回収したCO2の7割以下だった場合に1・2割の減額という非常に甘いペナルティしか課していない。逆に言えばほとんど稼働せず、実態としてCO2削減になっていなくても、既設火力をCCS付に改修さえすれば8~9割の容量確保契約金が受け取れるようなしくみとなっており非常に問題である。
なお、CCS付改修はコストも高く、需要側の負担増につながるだけで、環境性だけでなく、経済性も見合っていない。
②水素・アンモニア・CCSなど既設火力の改修は対象外とすべき
既設の火力発電所を直ちに完全に脱炭素化するのは現実的に不可能である。長期脱炭素電源オークションの対象として水素・アンモニア混焼設備、CCS設備追加の改修を対象からはずすべきである。
パリ協定の1.5℃目標を達成するには、2030年までに石炭火力の全廃、2035年までには電源の完全な脱炭素化が求められている。このため、最優先で取り組まなければならないのは、短時間で設置が可能でコストも安い再生可能エネルギーへのシフトであり、そこに投資を集中させるようなしかけが必要だ。本制度では、過去2回の結果を見ると太陽光や風力、水力に関しては応札がゼロ件だった。
石炭へのアンモニア混焼は20%と混焼率も低く設定されているので、8割分は引き続き石炭が燃料として活用され続けることになる。しかもアンモニアの製造プロセスでのCO2排出は問わず、グレーアンモニアも認めている。この場合、ほとんど削減効果がない上に、費用ばかり莫大にかかり、電気代高騰に繋がり国民負担増につながる。
③LNG専焼火力は脱炭素に逆行。対象から外すべき
LNG専焼火力を長期脱炭素電源オークションの対象から外すべきである。
LNGは化石燃料であり、CO2の大量排出につながる。燃焼時のみならず、生産・輸送段階でも大量のCO2を排出し、気候変動の悪化を招く。「化石燃料からの脱却」というCOP28の合意を守り、新規建設を促すべきではない。2025年のオークションで落札となれば8年後の2033年までに稼働することとなり、日本がNDCで提出した2035年60%削減、2040年73%削減という温室効果ガス削減目標の達成も危うくするものである。
④長期脱炭素電源として新設を推進するのは再エネ・蓄電池に限定すべき
気候変動対策として対応しなければならないのは、CO2を排出しない再エネを増やし、再エネの割合を高めるために必要な系統増強や蓄電池などの導入を増やすことである。火力や原子力は温室効果ガス削減の効果がほとんどなく、石炭火力については、混焼やCCS付への改修をすることで、延命につながり長期に渡ってCO2の排出を引き延ばすことにつながる。「長期脱炭素電源」を増やすために、このオークションのようなしくみを使って新規電源を増やすのであれば、対象を再エネや蓄電池に限定することが必要だ。
その方が費用対効果も高く、時間的にも早く脱炭素化が進む。
3.募集量について(P16~)
①脱炭素火力
脱炭素火力は、グリーン水素・グリーンアンモニア専焼に限定すべきである。また、その際、上限価格を水素やアンモニアのみ特別扱いせず、他の電源と同程度とし、コストの安いものから落札することを原則にするべきである。
また、既存火力の改修は、水素・アンモニア・CCSともに導入すべきではない。しかも、今回の見直し案では上限価格が平均40万円などとして非常に高額で他の電源の倍以上としており、需要家に過度な負担となる。「需要家負担にも配慮し」募集量を100万kWから50万kWに引き下げるくらいなら、その全量分を再エネや蓄電池に回し、価格を安く抑えれば需要家にとっても負担は減り、その方が環境的にも経済的にも合理的である。また、既存火力に改修しても、将来的にその設備のまま水素やアンモニアの専焼にできるわけではなく、専焼専用の別の発電設備へのリプレースが必要となる。水素・アンモニアの混焼やCCS付への改修は、供給力提供開始期限が11年(法・条例アセス済・不要の場合:7年)としており、事実上7年間、対策がとられていない既存の火力発電所が動き続け、その後もわずかアンモニア20%程度の混焼で化石燃料がメインの燃料であることには変わりない。いずれにしても火力の延命策でしかなく、全く気候変動対策に貢献せず、「脱炭素火力」などと呼ぶべきではない。
②既設原子力の安全対策投資
既設原子力の安全対策投資を新規電源開発などと同等に位置づけて、原子力の再稼働・延命を図るべきではない。今回150万kWもの規模を確保しているが、既存原発安全対策は老朽原発を含む原発の延命策にほかならず、新規電源開発を促すこの制度の主旨にあわない。
③蓄電池・揚水・LDES(P17)
募集上限を100万kWから80万kWに減少させるべきではない。特に蓄電池はこれまでのオークションで募集量を大幅に超えるような入札があった。募集量を減少するのではなく、むしろ増やして大量導入を進め、現在各地で問題となっている再エネ余剰電力の出力制御を止めるための対策に積極的につなげていくべきだ。
④LNG専焼火力
LNG専焼火力は対象から外すべきである。
2023~2025年度の3年間で600万kWとしていたものが、初年度で大半が落札され、追加募集枠を400万kWも増やし、合計で1000万kWにもしようとしている。これらが全て稼働すれば、年間3000万トンものCO2の排出につながる懸念があり、完全に脱炭素の方向に逆行している。
4.入札価格の在り方について(P21~)
①事業報酬率
建設リードタイムが長い電源種ほど事業報酬率を高く設定する措置に反対である。
建設リードタイムが長い電源種と短い電源種の比較で「事業報酬率が同じであり、建設リードタイムが異なる投資先の候補がある場合、投下資本の早期回収の観点から、建設リードタイムが短い案件への投資が選択されやすいが、これでは、建設リードタイムの長い案件への投資が促進されず、エネルギ ーミックスの観点から望ましくない」などとし、「事業報酬率は 5%をベースとし て、建設リードタイム(供給力提供開始期限)が10 年以上の長い案件はリスクプレミアム 1%加算できることとし、5 年未満の短い案件は 1%減じる」としている。一般水力・揚水・水素・アンモニア・CCS・原子力は事業報酬率を6%とし、太陽光・風力・地熱、蓄電池、LDESを4%とし、原子力や火力に手厚い措置をとっている。建設リードタイムが短ければ、短期間に気候変動対策に効果を発揮することができ、削減効果を大きく得られることを考えれば、むしろ、建設リードタイムが短いものを早く大量に普及させるしくみにすることが重要だ。
②インフレ、金利変動等への対応(事後の自動補正)(P22~)
電力事業者側からの要望に応じて応札価格に含まれる各費用を多様な指標で自動補正する形としたが、将来の需要側の負担を不透明にするばかりか、過重な負担を強いることが懸念されるため反対である。
本とりまとめでは、昨今のインフレによる建設費・金利の上昇や、為替の大幅な円安の状況を踏まえ、「大型電源については投資額が大きく、総事業期間も長期間となるため、収入・費用の変動リスクが大きく、そのようなリスクに対応するための事業環境整備が必要」などという意見を考慮して、①資本費については運開時の1回に限り建設工事デフレーター(電力)で補正、②運転維持費については企業物価指数(総平均)で補正、③水素・アンモニア・CCSの可変費については為替レート、海外の消費者物価指数等で補正、④事業報酬については運開時の1回に限り建設工事デフレーターで補正に加え、1年毎に日本銀行の貸し出し約定平均金利で補正など、事後的な費用変動にきめ細かく対応する形となっている。このような措置は、事業者のリスクを回避する一方で、需要側に想定不可能な負担を将来的に強いることになり、しかもそれが累積的に莫大な増加を招くことが懸念される。特に、水素・アンモニア・CCSなど将来的な燃料価格が非常に高額になることが想定される可変費を新たに加えた上に、さらにこのような措置をとるべきではない。
③事後的な費用増加への対応(P27~)
原発の事後的費用増加での落札価格の修正案に反対する。
今回、物価変動や金利変動に対応する自動補正を導入することとしたのに加えて、大型電源の新設・リプレース投資については、法令対応等の他律的に発生する費用増のリスクが大きいとし、リスク対応のためのしくみが提案されている。対象となるのは、供給力提供開始期限が10年以上、かつ設備容量が30万kW以上の電源とするが、つまり事実上原発の建設費が増加することを念頭においた特別な措置である。
「事後的な費用増加を際限なく落札価格に反映することは、需要家負担への 影響の観点からも、望ましくない。」として1.5倍を上限としているものの、エネルギーの国民負担を下げるという政府の方針に反しており、なんら合理性がなく、1.5倍の範囲としても追加すべきではない。
5.上限価格について(P31~)
①閾値の引き上げ
過度な国民負担の発生を防止するため安易な閾値の引き上げ(平均10万円から20万円に引き上げ)に反対である。
これまでの入札で、蓄電池で募集量を大きく超える応札があり、他の電源で募集がなかったのは、蓄電池に競争力があることの証左である。また、再エネの応札がないのは、FIT制度が並走していることも考えられる一方、本制度における太陽光や風力などの設備容量の設定(1万kW)が大きすぎて現実的な規模感ではないと考えられる。上限価格を引き上げれば、総じて需要家の負担を増幅させることにつながり、国民負担を下げるという本来のエネルギー政策の趣旨に反する。安価な電源が大量に導入されるようなしくみにするべきで、安易に閾値を引き上げるべきではない。
②水素・アンモニア・CCSの上限価格・可変費の支援範囲(P32~)
「水素・アンモニア・CCS 付火力の上限価格は、閾値 20 万円/kW/年 に関わらず、導入が可能となる水準まで引き上げる」ことに反対である。
今回の案では、水素・アンモニア・CCS付火力の可変費を、LNG・石炭の燃料代との価格差部分に限定し、設備利用率4割分までを応札価格に算入可能としている。「設備利用率 5 割分の可変費を支援対象とした場合、実際の設備利用率が 5 割を切れば過剰支援となる」などとしているが、事業者が本来とるべきリスクをすべて需要側に委ねるような歪んだ制度をつくるべきではない。
前述したとおり、水素・アンモニア・CCS付火力は、「脱炭素電源」ではなく、CO2を大量に排出する「大規模排出電源」である。グレー水素やグレーアンモニアの場合は、ライフサイクル全体で見たときに、CO2の排出削減にはほとんど貢献しておらず、場合によってはCO2が増えてしまうことにもなりかねないようなものだ。それに対して、上限価格を他電源の倍以上に設定し、入札をかき集めるのは環境的・経済的に全く合理性に欠ける。絶対に導入すべきではない。
6.リクワイアメント・ペナルティ等(P45~)
①年間混焼率リクワイアメント
水素アンモニア混焼の火力発電で設備利用率が40%以上を上回った場合にペナルティを緩める措置は気候変動対策に逆行するため反対である。
そもそも水素やアンモニア混焼を本制度の対象にすること自体反対であるが、本とりまとめの案では、「需給の状況によって実際の設備利用率が 40%以上に高くなった場合には、水素・アンモニアによって発電できず、LNG・石炭で焚き増しを行わざるを得ないことも想定される」として、このようなケースで「年間最低混焼率リクワイアメントを満たせない場合にペナルティを課すことは酷」として年間最低混焼率リクワイアメントの内容を緩和する案を示している。この想定は、状況的に化石燃料を焚き増ししてCO2排出量が非常に多くなることを意味しており、「脱炭素」ひいては「気候変動対策」に逆行している。本来の目的から考えても本末転倒である。
7.委員名簿(P51)およびオブザーバー名簿(P52)
本案に全面的に反対するとともに、偏った構成メンバーの見直しを求める。
長期脱炭素電源オークションの第3回の案は、これまで以上に原発や火力の維持のために事業者のリスクをほとんど全て丸抱えするようなしくみであり、再エネ事業の競争力を削ぎ、再エネや蓄電池の安価で短期導入可能なメリットを引き出すどころか潰すしくみで、かつ需要側の負担を著しく増加させるもので、不公正も甚だしい。
このような案を決めた委員は、大手電力会社や事業者に非常に偏った構成で、かつ火力や原子力事業に関わる当事者たちがオブザーバーとして参加している。まとまった案は、大手電力会社などのオブザーバーが自由に発言して、彼らが全て納得する形でつくられた内容である。一方、需要側である消費者団体や、環境団体の参加は皆無で、発言の機会すらなく、全て決まった後に形式的なパブコメがなされているだけである。
このような歪んだ構成で、国民生活や電力料金に直結するようなしくみが決められることは非常に問題である。委員およびオブザーバー参加の構成を見直し、広い意見が取り入れられるようにすべきである。
参考
電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会第二十二次中間とりまとめ(案)等に対する意見募集について(PDF)
お問い合わせ
本意見書についてのお問い合わせは以下よりお願いいたします。
特定非営利活動法人 気候ネットワーク
(京都事務所)〒604-8124 京都市中京区帯屋町574番地高倉ビル305号(→アクセス)
(東京事務所)〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目12番2号藤森ビル6B(→アクセス)
075-254-1011 075-254-1012 (ともに京都事務所) https://kikonet.org