
「Kiko」は、温暖化問題の国際交渉の状況を伝えるための会期内、会場からの通信です。
会議場通信 Kiko ベレンNo.4(2025年11月20日)
グローバル・ムチラオンを実現できるか:最終交渉の行方
18日(火)に、決定文書の草案および議長からのレターが公表され、現地で会議を傍聴しているNGO等にも、合意の全体像が少しずつ見えてきた。
Belém Political Package
議題採択されず、その後、議長によるコンサルテーションが行われた4つのテーマ(NDC、透明性、気候資金、貿易に関する一方的措置)については「Mutirao Decision(ムチラオン決定)」と名付けられた文書にまとめられるようだ。ほか、公正な移行作業計画(JTWP)や適応に関する世界全体の目標(GGA)、緩和作業計画(MWP)といった議題の決定文書が続く。グローバル・ストックテイク関連の3つの議題は一つにまとめた文書となっている。ムチラオン決定と主要議題の合意文書をまとめて「Belém Political Package(ベレン政策パッケージ)」として、19日にも合意をしたいとした。他の議題については21日の合意をめざす。
ただし、公表された合意文書案については、いまだオプションやブラケット(括弧付き)が残っており、特にムチラオン決定については、閣僚級での意思決定を行うためには、もうひと段階、内容をまとめる必要があるだろう。19日にも第2草案が出ることになっているが、執筆時点ではまだ発表されていない。
ムチラオン決定に盛り込まれた内容は多岐にわたるが、Kikoが注目したいのは、化石燃料からの脱却に関する記載が、どの程度、合意内容に入るかどうかだ。前号でお伝えしたとおり、COP28の第1回グローバル・ストックテイク(GST)の成果文書で「化石燃料からの脱却」「再エネ3倍」「エネルギー効率倍増」をしていくことが合意されてから、その実施をどう促すかが論点となっていた。
ここまでに公表されている文書では、JTWPの非公式ノートに盛り込まれているほか、ムチラオン決定文書案のパラグラフ44のオプションの一つとして残っている。このオプションではNDC統合報告書および隔年透明性報告書(BTR)統合報告書について毎年のCOPで検討することが提案されている。NDCの強化と実施を促すことを目的とし、具体的な内容としてGSTの成果に沿ってこの重要な10年において再エネ3倍、エネルギー効率倍増、化石燃料からの脱却等の行動を加速させていくことが含まれている。
化石燃料からの脱却が合意文書に盛り込まれるかどうかについては、産油国等一部の締約国からの反発も大きく、一筋縄ではいかないだろう(交渉議題はいずれもそうであるが)。細かい表現や文言についての議論と調整が行われるものと思われる。
化石燃料からの脱却ロードマップ策定への賛同
ルーラ大統領のスピーチをきっかけに浮上してきた「化石燃料からの脱却ロードマップ策定」に賛同する締約国の動きもある。ロードマップ策定をCOP決定に入れることに賛同する国は18日時点で80カ国を超えたという。18日には、マーシャル諸島、ドイツ、コロンビア、ケニア、UK、シエラレオネら十数カ国の閣僚が共同記者会見を開催し、化石燃料からの脱却ロードマップの策定を決定文書に入れることを求めた。こうした締約国の動きがどこまで影響するか。なお、日本はこの動きには入っておらず、18日に現地でスピーチをおこなった石原環境大臣は、取材に対し、水素やアンモニアを活用し脱炭素火力として置き換えることが日本の方針であると答えたと報じられている。
2週目に入り、水面下での交渉が続くなか、どのように交渉がまとまっていくのかはなかなか見えづらい。ムチラオン決定の副題には「気候変動に対し世界全体で行動し、人類が結束する(uniting humanity in a global mobilization against climate change)」と書かれている。気候変動問題に人類が結集し立ち向かう姿=グローバル・ムチラオンを体現し、1.5℃目標達成に向けた機運を高めていく内容となることを期待したい。
(執筆:ベレン時間11月19日(水)午前中)
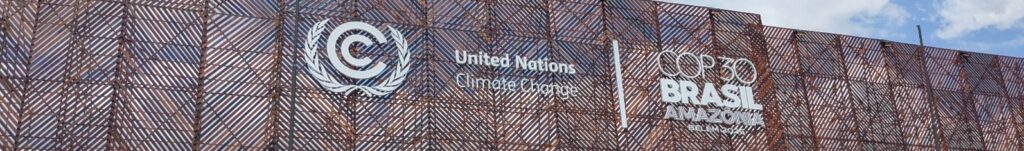
化石燃料脱却に向けた各国の動き次々と
11月17日、化石燃料からの脱却に関する2つの枠組みで大きな動きがあった。
韓国、バーレーンのPPCA加盟
PPCA(脱石炭国際連盟)は、石炭火力発電からの脱却とクリーンエネルギーへの移行を目指す国際的な枠組みである。COP23での発足以来、そのメンバーを増やしてきた。PPCA加盟には、OECD諸国とEUは2030年まで、その他は2040年までの石炭火力フェーズアウト宣言が求められている。18日に開催されたPPCA主催のイベントにて、キム・ソンファン気候・エネルギー・環境大臣が韓国の加盟を宣言し、会場は大きな拍手に包まれた。韓国は世界第7位の石炭火力発電所の設備容量を持ち、東アジアでは国として初めてPPCAに加盟した。キム大臣は「石炭からクリーンエネルギーへの移行は、気候変動問題への取り組みにとって重要というだけではなく、エネルギー安全保障を強化し、企業の競争力を高め、将来の産業に多くの雇用を生む」とコメントしている。また、PPCAのプレスリリースによると、バーレーンも加盟した。
カンボジアの「化石燃料不拡散条約」への参加
同日、COP30アクション・アジェンダのハイレベルイベントにてカンボジアが「化石燃料不拡散条約」イニシアティブへの参加を発表した。アジアでは東ティモールに続いて2カ国目、世界全体では18カ国目の参加となる。同イニシアティブは「核不拡散条約」にならい、化石燃料の拡大を停止し、再生可能エネルギー利用へと転換するための国際的枠組みづくりを提案している。
アジアの国々が化石燃料フェーズアウト、再エネへの転換をめざすなか、日本はそのどちらにも参加していない。日本政府は2025年の2月の期限内にNDC(2035年の排出削減目標)を提出した。問われるのはその中身である。石炭、さらには化石燃料フェーズアウトを宣言し、再エネへの転換を進めていくことが次に世界から求められる役割であろう。
我々が求めるCOPとは (ECO抄訳11/17)
COPの有用性を疑問視する声があるという噂を耳にしている。何千人ものロビイストが進捗を妨げ、環境保護に取り組んでいると見せかけるためにやってくるなんて、まさにグリーンウォッシュだ。では、COPを止めるべきだろうか?早まるな、COPという場は壊してはならない(そんなことになったら横暴な気候変動懐疑論者や化石燃料生産者たちを喜ばせるだけだ)。答えは、改革にある。効果的で公平な意思決定を促進し、説明責任を確保し、さらに化石燃料の支配から抜け出すため、プロセスを再調整しなければならない。実現に向けてECOがいくつか提案しよう。
- 交渉以外の成果に対する説明責任の実行とグローバル気候アクション・アジェンダの監視と検証の推進
- UNFCCCが企業に牛耳られないように、具体的な措置を通じて大規模排出企業をつまみだせ(#KickBigPollutersOutを付けて投稿しよう)
- UNFCCCプロセスにおける透明性を高める
- 市民社会の活動の場を守るべく、公正なホスト国協定と強力な人権保護措置を通じて、参加の機会、アクセシビリティ、費用負担の軽減を確保
ECOは、締約国、議長国、そして事務局に対して、要請する。一歩踏み出し、共に我々が求めるCOPを実現させよう。(そして#TheCOPWeNeedを付けて投稿しよう)
資金の話 (ECO抄訳11/18)
昨年の気候資金合意(NCQG)について一部の締約国は今でも歓迎の意を示す。他方で絶望と怒りを込めてパリ協定の約束に対する裏切りだという国もあれば、大笑いする国さえある。しかし昨日の適応基金の拠出国による対話では、昨年指摘されていたことではあるが、NCQGが茶番にしか見えないと確認されたようだ。
適応に関する世界全体の目標(GGA)の結果が極めて重要となっている今年は、NCQGにとっての試金石だ。ECOは、NCQG合意に沿って多国間気候基金からの拠出金を3倍にする目標達成まで、4年しか残っていないと締約国に思い出させよう。
途上国への公的資金の拠出について言えば、パリ協定9条1項をめぐる駆け引きは完全なコメディの様相を呈しているが、実際にはこれ以上ないほど深刻な問題だ。国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見により先進国の法的義務が改めて明言された。NCQG合意の結果として信頼が損なわれたことを踏まえると、資金提供において、先進国は信頼を再構築する必要性に迫られている。
締約国は、自らの約束を真剣に履行する意思があると証明できるのか。締約国は3,000億ドルの資金調達を行うための現実的な計画を示し、計画された責任分担を明らかにする具体的かつ期限付きの目標を示すべきだ。
※ECOは、気候変動問題に取り組むNGOの国際ネットワークClimate Action NetworkがCOPなどで発行しているニュースレターです。
会場通信Kiko COP30 CMP20 CMA7 No.4
2025年11月20日 ブラジル・ベレン発行
執筆・編集:浅岡美恵、鈴木康子、菅原怜、榎原麻紀子、森山拓也、田中十紀恵、中西航


