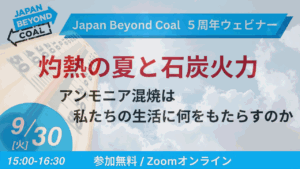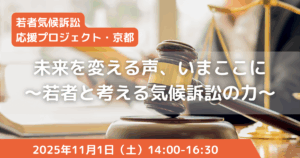気候ネットワークは、北陸電力による富山新港火力発電所 LNG2号機建設計画に係る環境影響評価方法書に対し、意見書を提出しました。
資料閲覧や意見提出はこちらから(意見書の提出期限は2025年10月14日消印有効)
この計画の概要
- 北陸電力は、富山新港火力発電所において、石炭2号機および休止中の1号機(石油)を廃止し、LNG2号機を導入する計画の検討を開始。LNG2号機の運転開始時期は2033年度の予定。
- 新設するLNG2号機の出力は60万kWで、廃止する石炭2号機(25万kW)、1号機(石油)(24万kW)の合計を上回る。
- 北陸電力は、中長期的には燃料としてアンモニア・水素を導入する等により、2050年カーボンニュートラルを目指すとしている。
- 北陸電力はLNG2号機の建設計画と同時に、2024年度までとしていた富山新港火力発電所の石炭1号機の廃止を2028年まで延期すると発表。北陸電力はもともと、石炭1号機はLNG1号機の導入に合わせ2018年までに廃止するとしていたが、廃止時期を2024年まで延期していた。今回の延期は2度目の約束違反となる。
① 第7次エネルギー基本計画や日本政府の温室効果ガス削減目標を事業の正当性の根拠とすべきでない
貴社は、本事業の目的(方法書p.3)および計画段階配慮書に対する意見への回答(方法書pp.329–333)において、本事業が第7次エネルギー基本計画ならびに日本政府の温室効果ガス排出削減目標と整合していることを繰り返し主張し、事業の正当性の根拠としています。
しかしながら、これらの政府目標は、国内外の科学者コミュニティから一貫して「不十分である」と指摘されてきました。国際的な研究機関コンソーシアムであるClimate Action Trackerの報告【注1】によれば、日本がパリ協定の1.5℃目標と整合する排出削減を達成するためには、2013年比で2030年までに66%、2035年までに78%の削減が必要とされています(LULUCF部門の吸収量を除く)。これに対し、日本政府が掲げる2030年度46%、2035年度60%、2040年度73%削減(いずれも2013年度比)の目標は、先進国としての責任を果たすには不十分であり、国際的な水準と比しても野心性を欠いています。
さらに、第7次エネルギー基本計画は2040年時点においても化石燃料への依存を前提としており、IEAの「Net Zero by 2050」シナリオが示す「天然ガスによる発電量を2030年にピークとし、2040年までに90%削減する」という方針や、G7が合意した「2035年までの電力部門の脱炭素化」とも整合していません。
以上の点から、本事業の根拠とされる国の方針そのものが、1.5℃目標および国際的な科学的要請から乖離しており、これをもって新規LNG火力発電所の建設を正当化することはできないと考えます。
【注1】https://climateactiontracker.org/press/release-as-the-climate-crisis-worsens-warming-outlook-stagnates/
② 気候科学の観点からみれば、化石燃料インフラの新規建設の余地はない
貴社は本計画を、石炭火力廃止に伴う脱炭素化と説明しています。しかし、LNG火力は石炭より排出係数が低いとはいえ、依然として莫大な二酸化炭素を排出する化石燃料発電です。さらに、採掘・輸送・液化・再ガス化までを含むライフサイクル全体では、石炭よりも温室効果ガス排出が大きくなる可能性が最新の研究で指摘されています。
IPCC第6次評価報告書第3作業部会報告書(2022年4月公開)は、既存の化石燃料インフラが(2018年から)耐用期間終了までに排出する累積のCO₂総排出量を6,600億トン(報告書作成時点で計画されている化石燃料インフラからの累積総排出量を加えると8,500億トン)と予測しています。同報告書で地球温暖化を50%の確率で1.5℃に抑えるための限度として示されたCO₂の累積総排出量である5,000億トンを既に大きく上回っているため、科学的な観点から見れば、既存の化石燃料インフラであっても耐用期間の終了を待たずに廃止する必要があります。
LNG火力については、再エネ100%を目指す過程での経過措置として一定数の既設の発電所が役割を果たしますが、新規建設を進めるべきではなく、段階的廃止を目指すべきです。富山新港火力発電所LNG2号機が計画通り2033年に運転開始した場合、LNG火力発電所の運用年数を40年とすると、2050年を超えて大量のCO₂を排出するため、この新設を許容する余地はありません。
計画段階配慮書に対して提出された上記の懸念に対し、貴社は、再エネ電源の導入を拡大していく中においても、火力電源は供給力や調整力確保のために不可欠である、との見解を示しています(方法書p.329)。しかし、調整力の確保を理由に、長期にわたりCO₂を排出し続ける新規LNG火力発電所を建設することは、国際的な脱炭素の潮流と著しく乖離しており、合理性を欠きます。
調整力が必要となるのは、需要の急増や再エネの出力変動時など限定的な場面です。これに対応する手段としては、デマンドレスポンス、蓄電池、既存火力の柔軟な運用、広域系統連携の強化など、より環境負荷が低く経済的にも合理的な選択肢が既に存在し、急速に実用化が進んでいます。長寿命の化石燃料インフラに新規投資することは、将来的な座礁資産化のリスクが高く、そのコストは最終的に消費者に転嫁される可能性があります。
日本では「調整力=火力・蓄電池」といった限定的な議論がなされがちですが、海外では「柔軟性(flexibility)」というより包括的な概念が重視されています。柔軟性とは、電力系統の需給バランスを維持する能力であり、調整力のある電源(水力・火力)に加え、エネルギー貯蔵(蓄電池・揚水・温水)、系統運用、デマンドレスポンスなどが含まれます。IEA『世界エネルギー展望2022年版』では、2050年の世界の電源構成における再エネ比率が約9割に達すると予測されており、これは火力発電に依存せずとも柔軟性を確保できるという国際的な共通認識に基づいています。火力発電は柔軟性の一要素に過ぎず、排出削減の観点からは、火力新設以外の手段を優先的に検討すべきです。
また、貴社は火力電源の脱炭素化に向けて、アンモニアや水素といったゼロエミッション燃料の導入を検討し、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すとしています。しかしながら、この主張には具体性・実現可能性・経済合理性のいずれも欠けており、新規LNG火力建設を正当化するためのグリーンウォッシュに他なりません。
現時点では、安価かつ安定的なグリーン水素・アンモニアの供給見通しは立っておらず、仮に供給が実現したとしても、既存LNG設備での混焼・専焼には多額の追加投資と設備改修が必要です。導入時期、混焼比率、コストなどの具体的な計画が示されていない以上、これは希望的観測に過ぎません。不確実な未来技術への期待を根拠に、現実のCO₂排出から目を逸らしてLNG火力の新規建設を進める姿勢は、企業の社会的責任を放棄するものと考えます。
さらに、貴社は第7次エネルギー基本計画においてLNG火力の活用が「トランジションの手段」として位置づけられていることを根拠に、本計画が国の政策と整合していると主張しています。しかし、エネルギー政策は常に見直されるべきものであり、科学的根拠や国際的責務に照らして不十分な場合、企業はそれを超える野心的な行動をとる責任があります。国の方針に依存して排出削減を先送りするのではなく、LNG火力新設に充てる経営資源を、再生可能エネルギーの導入拡大や電力系統の柔軟性向上など、より確実で持続可能な脱炭素投資へと振り向けるべきです。
③ 石炭1号機の2度にわたる廃止延期は事業者の信頼を著しく損ない、非効率石炭火力の段階的廃止を求める政府方針とも矛盾する
LNG2号機建設計画と同日に発表された石炭1号機の2028年度までの運転期間延長は、気候科学の観点から受け入れられません。石炭1号機は旧式の亜臨界方式で、二酸化炭素排出量が多い発電施設であり、廃止を急ぐ必要のある非効率石炭火力です。
貴社は2010年に、石炭1号機を2018年度までに廃止する計画を発表していますが、2017年に廃止時期を2024年度まで延期しており、今回は2度目の延期となります。さらに、2018年に営業運転を開始したLNG1号機は、石炭1号機からのリプレースとして環境影響評価簡略化の対象とされています。それにもかかわらず、石炭1号機の廃止が計画通り行われないことは、浅尾慶一郎環境大臣が2月28日に「大変遺憾」と述べている通り、非常に問題です。
計画段階配慮書に対する上記の意見に対し、貴社は「短期的に十分な供給力を確保できないため、石炭1号機の廃止は困難」との見解を示しています(方法書p.329)。しかし、この説明は過去の約束を反故にするものであり、環境影響評価制度の正当性を損なうばかりか、脱炭素に向けた経営努力の欠如を露呈しています。
本来、LNG1号機の稼働開始と同時に石炭1号機は廃止されるべきでした。二度にわたる廃止延期は、需給見通しの甘さと、脱炭素への真摯な取り組みが欠如していることを示しています。
さらに、石炭1号機の延命は、非効率石炭火力の段階的廃止を求める政府方針とも明確に矛盾します。経済産業大臣意見(方法書p.256)においても、「非効率石炭火力のフェードアウト等を着実に実施すること」が求められており、石炭1号機の早期廃止は政策的にも当然の要請です。
以上の点から、石炭1号機の運転延長は、科学的・政策的・制度的観点のいずれから見ても正当化できず、貴社には計画の見直しと、脱炭素に向けた責任ある対応が強く求められます。
④ アンモニア・水素燃料の導入開始時期や、導入後の推定温室効果ガス排出量を公開すべき
気候変動による被害が深刻化する中、国際社会はパリ協定およびグラスゴー合意のもと、地球の平均気温上昇を産業革命前から1.5℃以内に抑えることを目指しています。この目標の達成には、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにするだけでなく、2030年までに排出量を半減させる必要があります。
IPCC第6次評価報告書は、1.5℃目標達成のために残されたカーボンバジェットが極めて限られており、選択肢も時間も非常に少ないことを明らかにしています。一方、国連環境計画(UNEP)が2024年10月に公表した「排出ギャップ報告書2024」【注2】は、世界の温室効果ガス排出量は依然として増加傾向にあり、現在の排出ペースが続けば、今世紀末には地球の平均気温が最大3.1℃上昇する可能性があると警告しています。
このような危機的状況においては、個別の発電所が排出する温室効果ガスも、気候変動の加速や地域の生活環境への影響という観点から、厳しく評価されるべきです。最新式のガスコンバインドサイクル方式であっても、IEAが1.5℃シナリオにおいて求める2030年の排出係数(0.138kg-CO₂/kWh)と比較して約2.5倍の排出量(0.32〜0.36kg-CO₂/kWh)を示しており、1.5℃目標との整合性を欠いています。さらに、LNG火力のライフサイクル全体を考慮すれば、石炭火力を上回る温室効果ガス排出となる可能性も指摘されています。
方法書(p.3, p.17)では、「中長期的にはアンモニア・水素といったゼロエミッション燃料の導入等により、さらなる二酸化炭素排出量の削減を視野に入れる」と記載されていますが、これを根拠に現時点での高排出インフラの新設を正当化することはできません。ゼロエミッション燃料の導入を主張するのであれば、少なくとも以下の情報を明示すべきです:
- アンモニア・水素燃料の導入開始時期
- 導入後の推定温室効果ガス排出量
- 導入に必要な追加設備・改修の内容とコスト
- 実現可能性に関する技術的・経済的根拠
これらの情報が示されない限り、「中長期的な削減の視野」は単なる希望的観測に過ぎず、現時点での大量排出を容認する根拠とはなり得ません。企業としての説明責任を果たすためにも、具体的かつ検証可能な情報の開示が求められます。
【注2】https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024
⑤ LNG2号機建設によって発電所全体の規模が増加するのに、減るように見せかけているのは問題
本事業の「あらまし」では、LNG2号機の建設によって富山新港火力発電所の合計出力は現状の166.47kW(石炭1号機・石炭2号機:各25万kW,1号機:24万kW,2号機:50万kW,LNG1号機:42.47万kW)から、約152.47kW(2号機:50万kW、LNG1号機:42.47万kW、LNG2号機:60万kW)に減ると示されています。
しかし、2020年10月から休止中の1号機(石油)を除けば現状の合計出力は142.47kWであり、LNG2号機の建設によって合計出力が増加することになります。さらに、本来は既に廃止されているべき石炭1号機が「現状」に含まれていることも問題です。
2023年に日本が議長として開催したG7広島サミットでは、「2035年までの完全又は大宗の電力部門の脱炭素化を図る」こと、「遅くとも2050年までにエネルギーシステムにおけるネット・ゼロを達成するために、排出削減対策が講じられていない化石燃料のフェーズアウトを加速させる」との文書(コミュニケ)が合意されました。気候危機回避のために化石燃料からの脱却が必要とされるなか、火力発電インフラの規模を拡大させる本計画が認められる余地はありません。
計画段階配慮書に対して当方が提出した意見でも、出力算定方法の不正確さと、それによる事業規模の誤認を指摘しました。しかし、貴社が方法書(p.329)で示した見解では、この核心的な問題に一切言及されておらず、回答として不十分です。さらに、今回の「環境影響評価方法書のあらまし」においても、LNG2号機の建設によって発電所全体の出力が増加するにもかかわらず、減少するかのような記述が繰り返されています。
改めて強調しますが、貴社が「あらまし」において休止中の石油火力1号機や、既に廃止されるべき石炭1号機を「現状」の出力に含めていることは、事業の実態を歪めるものであり、説明責任を果たしているとは言えません。LNG2号機の新設後の出力(152.47万kW)は、実質的に現状(142.47万kW)より増加しており、これは化石燃料インフラの拡張に他なりません。
このような説明は、気候危機対策として求められる化石燃料インフラの段階的廃止という国際的潮流に反するものであり、誤解を招く表現は厳に慎むべきです。貴社には、事業の実態に即した正確かつ誠実な情報開示が求められます。
⑥ 化石燃料インフラの新設はG7合意など国際合意と矛盾する
2023年に日本が議長として開催したG7広島サミットでは、「2035年までの完全又は大宗の電力部門の脱炭素化を図る」こと、「遅くとも2050年までにエネルギーシステムにおけるネット・ゼロを達成するために、排出削減対策が講じられていない化石燃料のフェーズアウトを加速させる」との文書(コミュニケ)が合意されました。
また、IEAが2021年5月に発表した「Net Zero by 2050」では、1.5℃目標に関するシナリオとして天然ガスについて「2030年までに発電量をピークとし、2040年までに90%低下させる」ことが示されています。
本計画はLNG火力である以上、再生可能エネルギーと比べ膨大な量の二酸化炭素を排出します。LNG火力の排出係数はガスコンバインドサイクルが0.32~ 0.36kg-CO2/kWh程度であり、これはIEAが上記の報告書で示した1.5℃シナリオで求める2030年の排出係数0.138kg-CO2/kWhと比べ約2.5倍にもなる数値です。2033年度に新規のLNG火力を運転開始する予定の本計画は、国際的な合意やシナリオに整合しているとは言えません。
計画段階配慮書に対して当方が提出した意見では、排出係数の具体的数値を挙げ、科学的根拠に基づく批判を行いました。しかし、貴社が方法書(p.330)で示した見解は、これらの指摘に正面から向き合うものではなく、国内のエネルギー基本計画への依拠や「検討中」といった抽象的な表現に終始しており、説明責任を果たしているとは言えません。
貴社は本事業の根拠として「第7次エネルギー基本計画との整合」「将来的な電力需要の増加」「ゼロエミッション燃料への転換可能性」を挙げています。しかし、エネルギー基本計画は科学的知見や国際的責務に照らして不断に見直されるべきものであり、現時点で不十分な計画に依存して新規投資を行うことは、将来的な座礁資産化のリスクを伴います。
国際的な研究機関コンソーシアムであるClimate Action Trackerの報告【注3】によれば、日本が1.5℃目標と整合する排出削減を達成するためには、2013年比で2030年までに66%、2035年までに78%の削減が必要とされています(LULUCF部門を除く)。これに対し、日本政府が掲げる2030年度46%、2035年度60%、2040年度73%削減(2013年度比)の目標は、先進国としての責任を果たすには不十分であり、国際的な水準と比しても野心性を欠いています。
また、データセンターや半導体工場などの電力需要増加が見込まれることを根拠に化石燃料火力の新設を正当化する見解も示されていますが、これらの事業者は再生可能エネルギーの調達を強く志向しており、RE100、気候変動イニシアティブ(JCI)、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)などに加盟する企業も再エネ拡大を競争力確保の要件として位置づけています。したがって、化石燃料による供給拡大は需要の実態と乖離しており、経済性の面でも持続可能とは言えません。
さらに、アンモニアや水素の混焼による「ゼロエミッション燃料への転換」についても、技術的・経済的に未確立であり、大規模導入の道筋は示されていません。こうした不確実な未来技術を前提に、現時点で高排出のLNG火力を新設することは合理性を欠き、企業としての責任を問われる行為です。
以上の点を踏まえれば、2033年に新規LNG火力の運転開始を目指す本計画については、パリ協定、1.5℃目標、IEAのシナリオ、G7合意などの国際的枠組みとどのように整合するのか、具体的かつ検証可能な形で説明することが不可欠です。
【注3】https://climateactiontracker.org/press/release-as-the-climate-crisis-worsens-warming-outlook-stagnates/
⑦ LNG火力インフラはライフサイクルで石炭火力よりも多くの温室効果ガスを排出する可能性がある
天然ガスの主成分はメタンであり、二酸化炭素の28~34倍もの温室効果をもつ強力な温室効果ガスです。「Environmental Research Letters」誌に掲載された論文【注4】によると、天然ガスの井戸、生産施設、パイプラインなどから少量のメタンが漏出するだけでも石炭と同程度の排出量になる可能性があります。また、2024年に「Energy Science & Engineering」誌に掲載された別の研究【注5】は、LNGは掘削作業によるメタン漏れが推定をはるかに上回っていることや、パイプラインによる輸送時の排出、液化・タンカーによる輸送を含めれば石炭よりもはるかに大きなエネルギーを要することなどを指摘し、20年間の温室効果ガス排出量を比較するとLNGが石炭よりも33%も大きいと明らかにしています。
こうした研究の指摘を考慮すれば、LNG火力の利用が地球温暖化対策になるとみなすことはできません。また、世界各地ではガス採掘、パイプラインの設置などにおける環境破壊や人権侵害が大きな問題となっているだけでなく、脱化石燃料への動きも高まっています。 2030年以降に新規のLNG火力発電所の運転を開始させるなどもっての外であり、LNG火力はカーボンニュートラルまでのつなぎ役どころか、気候変動を悪化させている主な要因の一つであることを忘れてはいけません。
計画段階配慮書に対して当方が提出した意見に対し、貴社は方法書(p.331)において「新設設備の建設や運用に当たっては、極力、燃料である天然ガスが漏洩しないように努めてまいります」との見解を示しました。しかし、これは問題の所在を発電所敷地内に限定するものであり、論点のすり替えに他なりません。
当方が指摘しているのは、ガス田での採掘、パイプライン輸送、液化、タンカー輸送など、発電所に至るまでのサプライチェーン全体における温室効果ガス排出の問題です。貴社の見解は、こうした上流過程の環境負荷に一切触れておらず、科学的な警告に対して「漏洩しないよう努める」という定量的根拠を伴わない精神論で応じているにすぎません。
科学的知見を軽視し、具体的な対策や説明を欠いた姿勢は、企業としての説明責任を放棄するものです。燃料の調達・使用に関わる事業者として、ライフサイクル全体における環境・社会への影響に責任を持つことは当然の責務です。
現状では、サプライチェーン全体のメタン漏洩を監視・検証する体制が十分に整っておらず、日本の事業者が輸入燃料の上流過程に対して実効的な責任を果たすことは構造的に困難です。したがって、こうした高排出リスクを内包するLNG火力インフラの新設は、科学的にも倫理的にも正当化できません。
【注4】https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ace3db
【注5】https://doi.org/10.1002/ese3.1934
⑧ 不確実で合理性のない「ゼロエミッション燃料」導入を前提に、化石燃料インフラへ新規投資すべきではない
貴社は本事業において、「本事業では、火力電源の脱炭素化に向け,中長期的にはアンモニア・水素といったゼロエミッション燃料の導入等により,更なる二酸化炭素排出量の削減を視野に入れ,2050年のカーボンニュートラルの実現を目指す」としています(方法書p.3, p.17)。しかしながら、水素・アンモニアの発電利用は、気候変動対策としても、発電コストの面でも合理性を欠いており、本計画の正当化根拠とはなり得ません。
富山新港火力発電所LNG2号機で将来的に利用を想定している水素燃料については、現状では商用発電に利用可能な水素の大半が化石燃料由来の「グレー水素」であり、製造・輸送過程での温室効果ガス排出を含めれば、ゼロエミッションとは到底言えません。水素燃料の有効性を評価するには、製造方法を含めたライフサイクル全体での排出量を定量的に示す必要がありますが、現時点でその供給体制や必要量の見通しは立っていません。
理論上、再生可能エネルギーによる電気分解で製造される「グリーン水素」はCO₂を排出しないとされますが、これは再エネ電力が余剰であることを前提としています。そのような再エネ電力が確保できるのであれば、電力として直接利用する方が高効率かつ低コストであり、わざわざ水素に変換して発電に用いる合理性はありません。
水素燃料は、航空・海運・製鉄など他に脱炭素手段がない分野に優先的に使うべきとされており、用途を特定したうえで供給体制を検討する必要があります。2023年のG7広島サミットでも、水素・アンモニアの利用には「1.5℃の道筋に整合する場合」など厳格な条件が付されており、脱炭素技術として無条件に承認されたわけではありません。
国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は2022年1月の報告書において、「水素は製造・輸送・変換に多大なエネルギーを要し、無差別な使用はエネルギー転換を遅らせる」と警告しています。また、IEAの「Net Zero by 2050」では、太陽光・風力・電動車がCO₂削減に大きく貢献する一方、水素やCCUSは実証段階であり、削減貢献度は低いとされています。
以上を踏まえれば、水素・アンモニア等のゼロエミッション燃料の将来的導入を口実に本計画を進めることは、日本の2050年カーボンニュートラル目標に整合するとは言えず、国際的な見解からも支持を得られないと考えます。
計画段階配慮書に対して当方が提出した上記の意見に対し、貴社は方法書(p.332)において、IRENAやIEAなど国際機関が示す課題には一切触れず、国内計画の記述を都合よく抜粋するのみの見解を示しました。これは、科学的知見を軽視し、国際的な合意を無視する姿勢であり、エネルギー事業者としての将来への洞察を欠いています。
また、貴社が「カーボンニュートラル化手段を断定せず幅広に検討する」「実現性を見極める」と述べていることは、現時点で本発電所の脱炭素化に関する具体的な計画が存在しないことを自ら認めているに等しく、極めて不誠実です。貴社が行っているのは「検討」ではなく、「新規LNG火力発電所の建設」という、後戻りできない化石燃料への巨額投資であり、不確実な未来技術への期待を根拠に、確実なCO₂排出源を固定化する(ロックイン)行為は無責任であると考えます。
さらに、貴社は第7次エネルギー基本計画を根拠に、再エネや蓄電池だけでは火力を代替できないと主張していますが、国の計画は非効率で将来性のない技術への投資を免責するものではありません。冬季の電力不足等の課題は、省エネの徹底、再エネ電源の多様化、デマンドレスポンス、広域系統連携、蓄電技術の導入などによって対応すべきです。LNG火力は既設設備の活用に留めるべきであり、長期にわたりCO₂を排出し続ける新設は、課題解決ではなく新たな問題の創出です。
具体的な脱炭素化の道筋を示さないまま、「将来ゼロエミッション燃料を使う可能性がある」とだけ主張することは、化石燃料プロジェクトを環境配慮型であるかのように見せかける「グリーンウォッシュ」と見なされても仕方ありません。