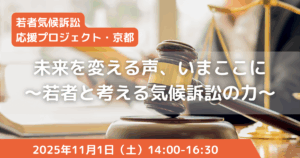2025年10月8日
特定非営利活動法人 気候ネットワーク
代表 浅岡 美恵
気候ネットワークは、次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会が行っている電力システム改革の検証を踏まえた制度設計に対して、以下の意見を提出しました。
意見募集ページ:https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/jisedai_kiban/002.html
提出意見
1. 電源投資を取りまく現状と課題について
「安定供給の確保が大前提」とし、脱炭素の両立をうたいながらも実質的に化石燃料への依存を正当化している。これは、気候変動対策の緊急性や国際的な脱炭素(化石燃料からの脱却)との整合性を損なうものである。
また、安定供給の確保を前提として、「容量市場、予備電源制度、長期脱炭素電源オークションなどの制度的措置を講じて対応を行ってきた」とし、今後も継続する方針を示しているが、これらのしくみが石炭火力を含め火力を維持温存し、CO2排出を固定化する元凶であり、抜本的に見直すべきである。
また、「投資環境の整備」が論点とされるが、この中で「気候リスク」についての議論が不十分である。国際的には炭素リスクを織り込んだ投資判断は主流であり、日本の制度設計をこの配慮なしで進めることは脱炭素投資の遅れと国際競争力の低下にもつながる。
なお、容量市場や長期脱炭素電源オークションなど容量メカニズムを見直し、再エネと再エネ最大限導入に必要な柔軟性措置で大胆なエネルギーシフトをし、海外に燃料を依存せず、エネルギー自給率を高め、環境に最も配慮した3Eの同時達成を実現できる電力システムを構築するために新たな容量メカニズムを構築すべきである。
2. 電力ネットワークの次世代化について
再生可能エネルギーの最大限の活用を可能にする設計 - 分散型・変動型電源(太陽光・風力など)を前提としたネットワーク構築が不可欠。そのために、既存の大規模中央集権型から、双方向・柔軟・地域分散型のネットワークへの転換が求められる。再エネの出力抑制や接続制約を最小化するための系統整備・運用ルールの改革が急務である。
また、ネットワーク投資の判断基準に、GHG排出削減効果や気候リスク回避効果を組み込む必要があり、その点が全く議論の俎上にない。
3-①. 小売電気事業者の量的な供給力確保の在り方(検討事項⑤)について
小売電気事業者の供給能力確保義務に反対する。本制度は多数の問題点があり、特に地域新電力のような小規模で再エネ調達を積極的に行う事業者にきわめて不利な内容になっている。
本制度は実需給年度の3年前に5割、1年前に7割の供給力(kWh)の確保を求めるものである。kWhの確保はかねてからJERAが主張してきたものだ。大口調達能力を持つ事業者が技術的な知見提供や交渉力で審議会の議論に存在感を発揮したことで、議論内容が大手の現実的ニーズに寄ったのではないかと思われる。実際に新制度は大手に有利な内容であり、JERAの提案に応じルールを変えてポジションを固定化するだけではないかという懸念が拭えない。2020年度の冬に発生した電力価格高騰時も含む4年もの間相場操縦をおこなっていたJERAの意見に国が追従する姿勢を強く懸念する。
そもそも新制度の有効性が十分に検証されていない。新制度が導入されれば、小売事業者は発電事業者との相対契約の確保に動くことが予想される。電源の大半が中長期の相対契約によって固定されれば、電力取引市場の流動性は低下し、ようやく活発化し始めた先物市場の勢いを削ぐおそれもある。取引コストの増加を招き、卸電力価格の上昇につながる可能性も否定できない。
一方で電源を持たない小売電力事業者は相対契約を増やさざるを得ず、調達手段やポートフォリオが制限され、競争力を失わせ市場から淘汰される恐れがある。
これは公平な競争環境を前提にした電力自由化に真っ向から反するものである。また、これまでの制度では変動型再エネが「供給力」に位置付けられてこなかったため、再エネ電源を確保した事業者が「供給力」として大手電力会社の原発や火力と相対契約せざるを得ない状況になれば、再エネのブレーキにもなりかねない。
すでに小売事業者は容量市場の容量拠出金で甚大な影響を受けており、制度設計にあたってはそもそもこの不公平な市場環境を見直すべきだ。
・日経エネルギーNEXT「新電力の3分の1が「容量市場値上げ」、大手電力はなぜ価格転嫁しないのか?」
・パワーシフト・キャンペーン「容量市場拠出金支払いの現状に関する調査」2024報告書
特に地域新電力は、地域脱炭素やエネルギーの地産地消による地域課題解決、再エネと地域の共生といった点で大きく期待されている。その伸長に水を差すことがあってはならない。
柔軟性(Flexibility)の重要性が国際的には広まっている中で、容量市場に続いて提案された本制度は柔軟性に欠けており、LNG火力などの大型電源への方向づけを強化するものであり、脱炭素化に向けて非常に深刻な問題がある。本制度の導入を見送ることを強く求める。
3-②. 中長期取引市場の整備に向けた検討(検討事項⑥)について
中長期取引市場では、限界費用だけでなく、発電所の固定費(資本費や維持管理費)も回収されることになる。容量拠出金と中長期取引市場で二重に固定費を支払うこととなり、公正な市場の在り方とは言い難い。大型電源を持つ旧一電など一部の事業者に有利な、より寡占的な市場となるだろう。これは「電気料金を最大限抑制する」「需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する」といった電力システム改革の目的ともほど遠い。脱炭素対策を進めるために最低限、電源に排出基準を定める、PPAやFIPを活用した変動性再エネへの投資が進む仕組みを構築するなどの対策を取らなければならない。そうでなければ、震災以前のように火力・原発が独占した、時代に逆行する市場となるだろう。
4. その他
再エネの主力電源化を徹底するべき
電力システム改革にあたっては、第7次エネルギー基本計画にも記されたとおり「再生可能エネルギーの主力電源化」を原則とし、そのための制度設計を実施するべきである。今回の3-①②からは、再エネの主力電源化よりもLNGの調達やLNG火力等の活用を強化する方向性が見て取れる。また、容量市場や長期脱炭素電源オークションは原発や火力を優遇するものであり、これからの主力を担うべき変動性再エネの存在感が全くない。
現在の電力システム改革の方向性は、G7の「2035年までに電力の大宗を脱炭素化させる」、COP28での「化石燃料からの脱却」との合意から明らかに逸脱しており、パリ協定にも違反している。電力システムの中心に再エネ普及を据えるよう、抜本から見直すべきである。
特に以下を求める。
- 現行の容量市場と長期脱炭素電源オークションの廃止または抜本的見直し
- 供給力の確保から、変動性再エネ+レジリエンス(柔軟性)確保へと市場の機能を抜本的に転換
- 運転コストが安い電源から順番に運転させるメリットオーダーや、ネガティブプライス(負の価格)の導入による再エネ出力制御の低減。出力制御が発生した場合の発電事業者への補償
意見募集プロセスに問題がある
本制度設計の方向性はきわめて重要であるにもかかわらず、意見募集が行われていることがわかるページが「第2回 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会」のサイトだけで、意見募集が積極的に行われているとはいいがたい。また、意見の提出方法もPDFへ入力の上メールしなければならないなど不便である。今回の意見募集とは別に、影響の大きい小規模な小売事業者から積極的にヒアリングを行うべきである。
お問い合わせ
本プレスリリースについてのお問い合わせは以下よりお願いいたします。
特定非営利活動法人 気候ネットワーク
(京都事務所)〒604-8124 京都市中京区帯屋町574番地高倉ビル305号(→アクセス)
(東京事務所)〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目12番2号藤森ビル6B(→アクセス)
075-254-1011 075-254-1012 (ともに京都事務所) https://kikonet.org