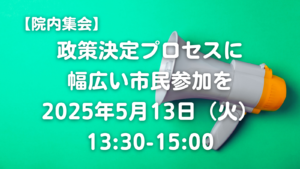2025年5月1日
特定非営利活動法人 気候ネットワーク
代表 浅岡 美恵
2025年4月25日、環境省は2023年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量を公表した。排出量はCO2換算で約10億1,700万トンとなり、2022年度比4.2%減少(▲約4,490万トン)、2013年度比27.1%減少(▲約3億7,810万トン)とされた。この排出量は昨年に続き「過去最低値を記録」したとして、「2050年ネット・ゼロの実現に向けた減少傾向を継続」したと説明している。そして、これらの要因として、「電源の脱炭素化(電源構成に占める再生可能エネルギーと原子力の合計割合が3割超え)や製造業の国内生産活動の減少によるエネルギー消費量の減少等」をあげている。
また、代替フロン等4ガス(HFCs、PFCs、SF6及びNF3)は2022年に減少に転じ、2023年はさらに減少した。さらに、森林やブルーカーボン等の吸収源対策で約5,370万トンを確保し、環境配慮型コンクリートによる吸収量(CO2固定量)で合計約121トンとなったことが公表されている。
2025年2月18日、地球温暖化対策計画が閣議決定され、政府は2030年目標については2013年度比46%削減を据え置きとし、2035年目標を60%削減、2040年目標を73%削減とする新しいNDC(国が決定する貢献)を国連に提出した。2023年度までの排出量推移は一見そこに向けて削減しているかのように見えるが、そもそも日本のNDCがパリ協定の1.5℃目標に整合しているとは言えず十分ではないことを指摘しておきたい。その上で、地球温暖化対策計画と同時に閣議決定された第7次エネルギー基本計画で示されたような原発・火力依存は、技術的・経済的にリスクが大きく、目標達成に留まらず2050年ネットゼロの達成も危うい。
今回公表されたところによると、2023年度に減少した主な要因は、原子力への依存と国内生産活動の減少によるものであり、再生可能エネルギーの大幅な増加や省エネの向上など排出削減に直結するまっとうな気候変動対策が機能した結果とは言えない。今後、原発のトラブルや社会経済情勢の変化によっては、増加に転じる可能性が捨てきれない。さらに、再生可能エネルギーを求めて製造業が生産拠点を国外に移転させることが増えれば、国内の電力消費・温室効果ガス排出量は減少するものの、産業の空洞化につながることも懸念される。
今年、GX推進法改正で排出量取引制度などカーボンプライシングの導入に向けた制度が整備されるが、1.5℃目標に整合する形で排出量にキャップをかけ、有償オークションを早期導入し、実質的な削減効果を持たせることがきわめて重要だ。また、電力市場においては、既存の火力発電所ならびに原子力発電所を延命させるための容量市場や長期脱炭素電源オークションを見直し、再生可能エネルギーの大量導入に合わせた電力システム改革を進めることで、2035年までの電力の脱炭素化を進め、国内の温室効果ガスの大幅削減を着実に進める道を選ぶべきである。
参考
環境省 報道発表資料:2023年度の我が国の温室効果ガス排出量および吸収量について
環境省 2023年度の温室効果ガス排出量及び吸収量(詳細)(PDF)
お問い合わせ
本プレスリリースについてのお問い合わせは以下よりお願いいたします。
特定非営利活動法人 気候ネットワーク
(京都事務所)〒604-8124 京都市中京区帯屋町574番地高倉ビル305号(→アクセス)
(東京事務所)〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目12番2号藤森ビル6B(→アクセス)
075-254-1011 075-254-1012 (ともに京都事務所) https://kikonet.org